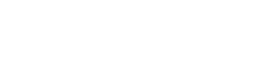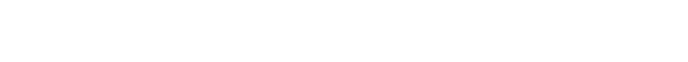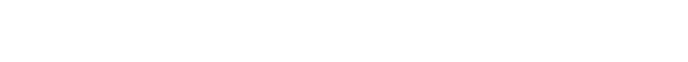作曲・演奏・テクスト 久保田翠
レコーディング 中村益久
ミキシング オノ セイゲン
鎌田岳彦
マスタリング オノ セイゲン
プロダクトデザイン 宇平剛史
ゲスト・ヴォーカル 小阪亜矢子
プロデュース 久保田翠
"Performance studies 6"
"Merei-träu"
"later"

作曲者自身によるいくつかの覚書
アルバム "later" をめぐって
「遅さ」について
ピアノ科受験をぼんやりと目指していた子どもの頃のように、「1日何時間」と決めて練習するようなことも少なくなった。自分の技量を維持するだけの最低限の練習時間を確保するのみである。
そうすると、必然的に練習をしない日がしばらく続くことがある。当然指の動きは鈍くなり、タッチが粗くなる。居心地悪さを思いながら、しばらく弾き続ける。
そんなときに初見演奏でもしようものなら、忽ちままならなさが身体にまとわりつく。目で見た情報が身体を通って音になる際のそのタイムラグは、まさにバッファリングとして身体を通過する。こんな時、自分の身体がバラバラと離散しているかのように感じる。そして実は、この感覚は私は嫌いではない。自分の身体はなんて脆いのだろうと思う。
ひきつづき練習を進める。次第に、鍵盤が再び近しくなってくる瞬間がある。ほんの少しの違和感を残しながらも、新鮮に鍵盤が寄り添ってくる。鍵盤を押し下げ、ピアノの底を打つその瞬間の打撃音………それは決して遠くには聞こえない………が快く手のひらに包まれる。そんな瞬間がとても愛おしい。
このまま練習時間を増やし、ある特定の曲を弾き続けるならば、やがて自分の身体はその曲を覚え、楽譜通り再現できるようになるだろう。考えずとも、弾けるようになるだろう。だが私はやがてピアノの前から離れ、自分の中に曲が定着しないうちに弾くのをやめてしまうだろう。なぜなら常に途上にあるのが楽しいのだから。放っておいても自動的に演奏できるようになると、音のためらいが消えてしまう。そのためらい………「遅さ」と言ってもいいかもしれない………にこそ、特別な何かが宿るのだから。

「演奏とドキュメンタリー」について
コンサートが始まる。もしも演奏初っ端で楽譜と違う音を出してしまい、思わず止まって曲の初めから再度演奏し直した場合、たいがいそれは「演奏の失敗」「不完全な演奏」としてみなされるであろう。そして再び演奏し直したそこからが「作品のはじまりだった」ということになるであろう。最初に演奏した音の連なりや、演奏し直す時に一瞬生じた空白の時間などは、作品「外」のものとしてみなされよう。
音楽が「一回性をもつ」とされるのは、そのような場における演奏のあり方を前提としたものであろう。奏者が目の前で演奏するスタイルの音楽作品は、そのように不可逆なものであり、一旦曲が始まってしまえば原則として最後まで途切れることなく演奏されなくてはならない。それは、例えば録音物として存在するある曲を、リスナーが途中で再生しなおしたり、自由に聴き飛ばしたりするということとはまったく別のあり方である。
だが、奏者が「初っ端で間違えた」時の、その音に現れた迷いや音の流れの澱みや、断片のように切れてしまったその曲の「冒頭部分」は、はたして意味のないものなのだろうか。「空白の時間」によって生じた緊張感は、単に不快なだけだろうか。
例えば街ですれ違った人の一瞬の表情や、歩きながら目の端に入った光景が強く印象に残ることがあるように、「出来損ない」の音が我々の耳にえもいえぬ印象を与えることもあるだろう。そしてその印象は、決してネガティブなものだけに留まらず、ある種のインスピレーションを与えてくれることだってありうる。ちょうど、「ドキュメンタリー」と呼ばれるジャンルの写真や映像において、撮影者の意図に反して映り込んだ誰かの眼差しに、我々が心惹かれ想像力を膨らませることだってあるように。
そう考えるならば、じつは一回ごとの演奏は、その都度奏者が生み出す「ドキュメンタリー」であるとも言えはしまいか。聴き手は奏者が繰り出す一音ごとの記録(及び記録作業)を目の当たりにしている。その一音一音の存在が、「作品全体」を超えてしまうことだってありうるかもしれない。それもまた、誠実に音に向き合うひとつのあり方である。

「疲労」について
アルバム《later》の中には、“Performance Studies” と名付けられた一連のソロピアノ曲が収録されている。ピアノで演奏してはいるが、実は作品としてはピアノ曲としてつくられたものではない。言葉のインストラクションによるパフォーマンス作品であり、任意の五線譜の作品をその都度異なる読譜方法で演奏する、というものである。
ただしその「インストラクション」もしくは「その都度異なる読譜方法」というのが、なかなか厄介である。たとえば、楽譜を上下逆にひっくり返し、そのまま左から右へと「普通に」読譜して演奏する。対位法の曲を選び、特定の声部のみ1小節遅らせて演奏する。右手は右上から「通常通りに」、左手は右下から左上へむけて「逆方向に」演奏するなど。
言ってみれば“Performance Studies”を実行するために必要とされるのは、「通常の」読譜方法とはかなり異なる仕方で楽譜に反応する身体であり、特殊な読譜方法はおそらく決して完璧に遂行されることはないであろう。それはつねに途上にある読譜技術である。
この作品では、いかにそれらのインストラクションを遵守するかが重要となる。そして演奏の段階で起こる「弾き間違い」「すっ飛ばし」「逡巡」などもすべてそのまま受け止めて演奏を続けなければならない(ちなみに演奏音源のミスした部分などを別テイクに差し替える、通常の音源ならば普通に行われる「編集」は、このCDにおいては全くおこなわれていない)。このような仕方は、当然のことながら奏者にかなりの疲労をもたらす。長年かけて覚えこんだ楽譜への反応の仕方は改変するよう迫られ、事前に備えることのできない数々の問いに、その都度応えていかねばならない。
演奏が終わると疲労は身体に蓄積し、思考は飽和する。これ以上の反応はできない、というところで、聴いたことのない響きが不意にこぼれ落ちる。通常の「十分に備えた」演奏からは引き出すことのできない、意図を乗せきれない音、といっても良い。誰かに撮られた写真によって自分の知らない自分の顔を知るように、過度なタスクを経た身体は、明らかに自分のものでありながら自分のものではない音をあらしめる。それらは危ういバランスで互いに連なりあい、不思議な響きを導き出す。だが弾いている間の私は、それを聴くことはできない。なぜなら目の前のタスクをこなすことで精一杯で、「音の連なり方」まで聴く余裕はないからだ。瞬間ごとに判断し、瞬間ごとに忘れてゆく。その結果ことを、私はのちに(later)録音を聴くことによって知ることになるのである。